大学過去問解説シリーズ!
今回は大阪大学 2023年度 全学部英語の解説です。
1(A)の解説はこちら、4(A)の解説はこちら、4(B)(イ)の解説はこちらです。
本記事では、大阪大学の過去問を使って解き方や考え方、要点を伝えています!
2次試験直前期の皆さんも本記事を読んで試験当日までラストスパート頑張りましょう!
英文和訳の攻略法
まずは、英文和訳問題共通して気をつけるべきポイントを3つ紹介します!
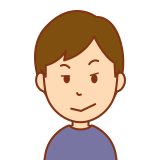
1.本文全体の意味を理解した上で下線部を訳す
2.文構造に注意して、「誰が」「どうした」を徹底的に捉える
3.冠詞・指示代名詞・名詞の単複など注意して訳す
どれも当たり前のことのように思えますが、意外と見落としているポイントです。
今回の記事では、一文一文丁寧に訳出していきますので、どういう頭の働かせ方をするのか、真似しながら読んでくださいね!
大阪大学英文和訳過去問
Ⅰ 次の英文(A)と(B)を読み、それぞれの下線部の意味を日本語で表しなさい。
(B) Ideas about creativity are as old as humanity even if the word ‘creativity’, in English at least, has been documented only since the 19th century. This is because the act of creating something is a defining characteristic of human beings . Historically, our appreciation for creative individuals has changed and, at different moments in time, certain individuals, professions, or activities have been more easily recognized as creative than others. But the general fascination for what makes creative people ‘stand out’ and what fuels their capacity to innovate remains constant through the ages.
(Glăveanu, Vlad . 2021. Creativity: A very short introduction. Oxford University Pressより一部改変)
ポイント1
本文全体の流れを捉えましょう。全体の時間配分も考慮すると、設問部分以外は文意が取れる程度の読みで大丈夫です。
Ideas about creativity are as old as humanity even if the word ‘creativity’, in English at least, has been documented only since the 19th century. This is because the act of creating something is a defining characteristic of human beings .
‘creativity’という言葉自体はとりわけ英語においては19世紀からのものだが、その考え自体は人類と同じくらいの歴史がある。それは、何かを作るという行為が、人間の特性を定義しているからである。
実際の問題箇所
第一文
Historically, our appreciation for creative individuals has changed and, at different moments in time, certain individuals, professions, or activities have been more easily recognized as creative than others.
①Historicallyは文頭に置かれています。文頭の副詞は文全体を修飾しますので、「歴史的には」と文全体にかかるように訳出しましよう。
②文の構造を捉えると、our appreciationからindividualsまでが主語、has changedが動詞であることがわかります。その後、andが現れるので何と何が並列されるのかに注意して構造をとります。
atからtimeまでは副詞句で「時間内の異なる瞬間において」が直訳です。その後、certain individuals, professions, or activitiesと3つの名詞が並置され、have beenという動詞が出てきます。hasではなく、haveが用いられていることからこの部分の主語は複数であることがわかり、直前の3つの並置された名詞ではないかと考えることができます。ここで、andは文と文を結んでいたことがわかりますね。
Historically, [our appreciation for creative individuals] has changed and, (at different moments in time), [certain individuals, professions, or activities] have been more easily recognized as creative than others.
③それぞれの文を見ていきます。our appreciation for creative individuals has changed の部分では現在完了が使われていることに留意して、「創造力のある個人個人への評価は変わってきた」などと訳せるといいですね。at different moment in timeは上述するように「時間内の異なる瞬間において」が直訳です。ただ、日本語としてやや不自然ですので後に続く文を見て、適切に訳語を変えることも必要でしょう。
certainはindividuals, professions, or activitiesの3つの名詞を修飾しています。動詞部分は比較の表現が用いられており、それらを含めて「特定の個人個人や、職業、活動は他よりも容易に創造的であると認識されてきた」となります。
これらを合わせると以下のような訳文になります。
歴史的には,創造力のある個人個人への評価は変わってきており、時間内の異なる瞬間において特定の個人個人や、職業、活動は他よりも容易に創造的であると認識されてきた。
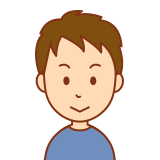
和訳の枠組みができたところで、この文が意図するところを再度考えてみましょう。
「創造力のある個人への評価が変化していること」と、
「時間内の異なる瞬間において特定の個人個人や職業、活動は他よりも容易に創造的であると認識されること」の間にはどのような関係があるのでしょうか。
時代によって、評価を受ける人々は違います。かつては評価を受けなかった人が日の目を見たり、一時代を築いた人々がいつの間にか影の存在になったりするわけです。つまり世間の創造性に対する評価が時代や場所によって異なることで、ある時代において特定の個人(時代にあった創造性を持つ人)が他の人と比べて”創造的である”と認識されやすくなってしまうのですね。
こういう文脈が伝わるように部分的に訳文を改訂します。
(意訳のような部分もありますが、本文が意図するところを最大限尊重しつつ使われている単語のニュアンスを表現するために、英語上の文構造と日本語における構造を一部変化させました)
歴史的に,創造力のある個人個人への評価は変化しており、その歴史のどこに位置するかによって,どのような個人個人や職業、活動は他のものよりも創造的であると認識されやすいかは異なっていた。
第二文
But the general fascination for what makes creative people ‘stand out’ and what fuels their capacity to innovate remains constant through the ages.
①Butから始まっていますね。一文目は時代によって変化するものがあるというニュアンスでしたのでこの文はおそらく「変化しないものもあると」いう文脈だろうと推測して読み進めます。
②構文としてとりにくいのは、for以下の部分でしょうか。whatからなる名詞節がandで並置されています。そこからfuelsは動詞で用いられていることが推測できますね。後ろに冠詞を含む名詞句があるのもヒントになります。動詞のfuelの意味がわかなくでもfossil fuels「化石燃料」という名詞から推測し、「燃料を与える」のような意味であることはわかるでしょう。
the general fascination for [what makes creative people ‘stand out’ ]and [what fuels their capacity to innovate]remains constant through the ages.
③whatから始まるそれぞれの名詞句ですが、構造自体はそれほど複雑ではありません。
what makes creative people ‘stand out’「何が創造的な人々を”際立たせる”のか」
what fuels their capacity to innovate「何が彼らが革新していく能力に燃料を与えるのか」
④文全体の構造は
the general fascination remains constant through the ages.
というシンプルな構造で、①の予想と合致しています。直訳で「一般的魅力は、時代を通じて変化しない」となります。
これらを合わせると以下のような訳文になります。
しかし、何が創造的な人々を”際立たせるの”か、何が彼らが革新していく能力に燃料を与えるのかに対する一般的魅力は、時代を通じて変化しないのである。
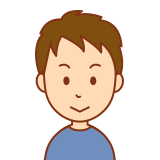
ここでもまた和訳の枠組みができたところで、この文が意図するところを再度考えてみましょう。
「革新していく能力に燃料を与える」の部分が日本語らしくないですね。本文の意図としては、「何によって創造的な人々の革新的なものを生み出す力が後押しされるのか」ということなので、「何が彼らの革新力を刺激するのか」や「何が彼らが革新できるように後押しするのか」などが良いでしょう。
また、「一般的魅力」という部分も不自然ですね、文全体の意図を汲んで「一般の人々が魅了されること」などとすると良いです。
しかし、何が創造的な人々を”際立たせるの”か、何が彼らの革新力を刺激するのかに対して一般の人々が魅了されることは、時代を通じて変化しないのである。
英文和訳解答例
歴史的に,創造力のある個人個人への評価は変化しており、その歴史のどこに位置するかによって,どのような個人個人や職業、活動は他のものよりも創造的であると認識されやすいかは異なっていた。しかし、何が創造的な人々を”際立たせるの”か、何が彼らの革新力を刺激するのかに対して一般の人々が魅了されることは、時代を通じて変化しないのである。


コメント